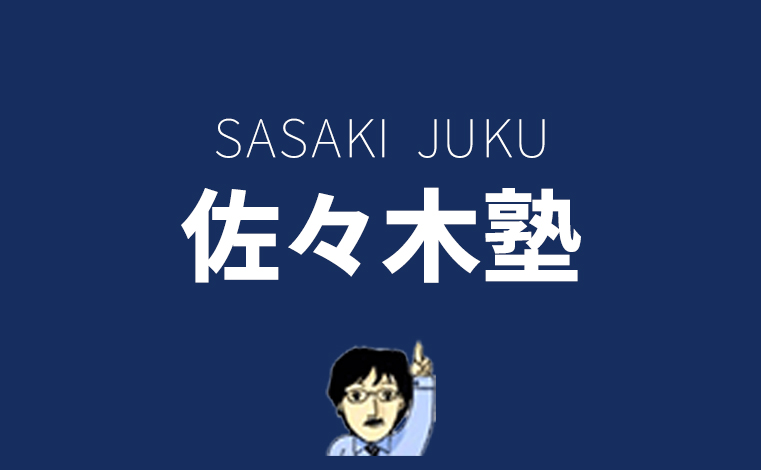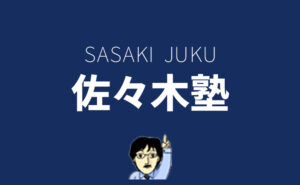「立川国際中等を受験予定だ」
「立川国際の小論文の対策方法を探している」
こんな人が読むとお役立ちの内容です。
東京都立川市にある立川国際を受験予定の保護者のみなさま。
東京都国立市にある佐々木塾では、3年連続で立川国際中学の小論文対策の指導を実施しています。
おかげさまで、3年年連続で小論文を指導していた生徒さんが合格して卒塾してくれました。ですので、このテーマにちょっとした自信があります。
この経験を元に、立川国際中学の小論文入試のポイントをお伝えしたうえで、当塾で行っている小論文の指導の概要をまとめました。
立川国際の小論文試験
適性検査の出題は、小論文と国語の融合問題であると考えた方が、理解しやすいです。
というのも、適性検査の出題は、5割は国語の出題範囲だからです。
評論文やエッセイを読んだ上で、問題[1]問題[2]問題[3]の3問出題されます。
問題[1]問題[2]は、国語のような問題で小論文は、問題[3]です。
ですので、問題[3]についてのみに話の照準を合わせます。
出題される問題は、本文の要約を前提にした上で、説明問題。そして、ありがちなのが「本校の学校生活でどのように活かしますか」という内容です。
設問には、年度によって違いますが、360〜400字の文章を書くように指定されます。原稿用紙一枚分です。
この字数(400字)のうちで、答えが本文の書かれてある(=国語の読解の記述問題)字数と自分の頭でイチから考えなければいけない字数文で分解しましょう。
年度や設問によって違いますが、一般論としてのバランスの話ですが、400字の場合120字・280字ぐらいのバランスが望ましいです。
120字は、答えが本文の書かれてあるので探しましょう。国語の解き方です。
残りの280字が、やっと小論文の出題になります。
「これは国語」「これは小論文」と分けるのがなぜ大事か。
「分ける」と「分かる」からです。
小論文というといかにも、ゼロから考えなければならないイメージがありますが、このように「小論文の名を借りた国語の問題」だと照射して正体がわかれば怖くありません。
「わからない」理由は、わけていないからです。
であると分けることができれば、これまでのパターン演習の試行回数の中から解答へのヒントが得られます。
なぜこんな話から始めたかと言うと、小論文だと構えて、これまでの知識(=国語の知識)で解けるのに、書けないという生徒さんが非常に多いからです。
話がすこし横道にそれたので、戻します。小論文の箇所280字は課題文には、書かれていません。
つまり、自分でゼロから考えなければなりません。
小学6年生といえども、ちゃんと読みやすい形で、文法正しく、漢字のミスゼロで合格点を取るのはかなり難しいです。大人が280Wordsで英語小論文を書く難しさと同じぐらいでしょうか。そのようにイメージすると、むずかしさが肌感覚で掴みやすいのではないかと思います。
まず、分解しましょう。
「本校の学校生活でどのように活かしますか」と訊かれています。
こういう出題の場合は、課題文の内容に沿ったテーマで、立川国際中学でがんばりたいことを書けば得点になります。
具体的には、英語、部活、小学校の頃より広がる人間関係の中での成長など、小学校にはなかったが中学から始まることについて、自分のしたいことを書けばいいのです。
佐々木塾の小論文指導のポイント
このように佐々木塾では、とにかく「わける」を意識して指導しています。
問題の出題パターンをわける目を養えば、ゼロからなにを考えればいいかわからないという混乱は避けられるはずです。
すると何がいいのか。小論文がパターン演習の積み重ねになります。いくつかのパターンを演習すれば、自然と書くことがわかりスラスラと立ち向かえるようになるわけです。
先述のとおり、「わからない」ということは「わけられない」ということです。
だからこそ、[課題文に答えが書かれている問題]と[自分の頭に考えなければいけない問題]はわけて考える必要があります。
さらに、[自分の頭に考えなければいけない問題]も、将来の夢を問われているパターン、学校生活で頑張りたいことを問われているパターン、友人関係での失敗を克服したエピソードのパターンなど、パターン化可能です。
そのために、佐々木塾では、全国の中学入試の小論文の入試問題を解いてもらって、毎週小論文を添削しています。
1年間だと40回くらい問題を解くことになるので、パターンは蓄積されていきます。すると、生徒さんの合格率が飛躍的に高まります。
適切に問題をわける→パターンにわける
3年連続で、立川国際の小論文を対策している中で、毎週添削することで、自分の文章の間違い方のパターンが蓄積されていきます。
間違い方のパターンは、けっこうどの生徒さんも似たり寄ったりになります。
したがって、面白いくらいに毎年似たような指摘が繰り返されます。
例えば、
・主語と述語がねじれてる
・時制を間違えていたり
・「ですます」と「である」が混在している
など
これらのミスが典型的です。
こうした指摘も、40週もやりとりしていくので、次第に消えていきます。
このように、自分の中にミスのパターンをストックしていくことで、研ぎ澄まされた文章ができあがっていきます。
何度も回数をこなして、毎度細かな指摘を復習する習慣ができると合格率は飛躍的に高まります。